コラムCOLUMN
「我が職業人生奮闘記」 岩城 全紀
- 第二章
- 北海道ティー・エル・オー株式会社勤務時代
(特許流通アドバイザー時代)- 【後編】「弁理士となってから」
| ・ティー・エル・オーに着任した頃 私が着任した平成12年7月は、同社の設立後間もない頃で、北海道大学を始めとする道内の各大学の特許制度に対する認知度も低く、技術移転の玉となる特許出願も皆無の状況であった。そのような中、まず、各大学の地域共同研究センターや研究協力課などを通じて、かような会社が設立されたことを、各大学の先生方に知ってもらう事が先決だった。 以下は、北海道ティー・エル・オー在籍時に特許流通アドバイザーの名簿に掲載された自身の画像である。 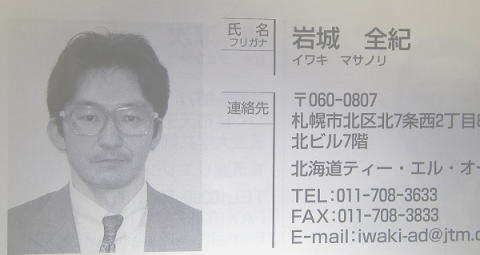 北海道ティー・エル・オー株式会社の取締役役員は、国立大学である北海道大学、北見工業大学などの教授先生、JR北海道や北海道電力、北洋銀行といった北海道経済界の重鎮といった方々を擁しており、又、特許庁の元技監(前述のN・S先生)の方を技術顧問として迎え入れるなど、体制的には整っていたと云える。前述のJR北海道や北海道電力、北洋銀行からは、社員の方々が出向して来られて事業部長や総務部長等、社内の要職に就いてもらい、会社の運営の一翼を担って頂くなど、オール北海道としてのバックアップ体制が採られたのである。 しかし、発明者となる大学の各先生方に、会社の性格、仕組みを知ってもらうには相応の時間が必要であり、本格的に発明が上がってきて、北海道ティー・エル・オーが出願人となる特許出願の件数が伸長するには、私の着任後1年ほどの時間が掛かった。 同社の転機となったのは、北大内の事務局の一室を、会社の拠点として提供してもらったことが、切っ掛けになったように思う。その北大内に拠点を構えたことで、北大内外の大学での認知度・信用度が向上し、発明相談を受ける件数が急激に増えてきた。当時は学内に知的財産本部もなかったことから、大学内の特許出願の窓口として、産学官連携に対し経験は浅いが、意欲十分な若手の先生方からの発明相談が多かったのも頷けることである。 また、ちょうどその頃、技術顧問のN・S先生が企画された「特許ビジネス講座」という、北大など理系の助教や講師などの若い先生方を対象とした、特許制度や技術移転に関する講座が、東京などから講師を招いて、北海道経済産業局の主催で行われたことが印象に残っている。今から20年ほど前の北海道は弁理士も少なく、大学の先生方の特許制度に対する理解もまだまだといった状況であった。この講座は、当時の知財後進地という状況を打破するために企画して実行されたと思われるが、講座の受講生からは数人の弁理士が輩出されたり、北海道ティー・エル・オーへの発明相談が増加する契機となり、さすがに中央官庁(経済産業省及び特許庁)で特許制度を牽引され、法改正にも携わられた方の企画力・人脈は大したものと感じたのである。 一方、TLO内での私の具体的な仕事は、先ず発明を発掘し(発明者である先生から発明内容等をヒアリング)、そして、会社に持ち帰った後に、その発明についての先行技術調査を行うとともに、特許性や実施可能性(ライセンス先の有無)などを検討する。次いで、特許出願に値すると判断した場合は、発明を社内の技術評価委員会に上程し、この評価委員会にて、TLOとして当該発明を扱うかどうかを審議して決定する。勿論、上程する以前の検討段階で、既に特許性を阻害する先行技術の存在が確認されたり、学会発表等が行われていて特許法30条の新規性喪失の例外規定の適用も難しいような場合は、その結果をヒアリングした先生にフィードバックして、取り扱いを断念することも幾度もあった。 TLOとして発明を扱うというのは、発明者である大学の先生と、TLOとが「特許を受ける権利」の譲渡契約を締結して、当該「特許を受ける権利」をTLOへ帰属させ、その上で特許出願に要する費用はTLOが負担するということである。そして、TLOは、特許出願を外部の特許事務所へ依頼するなどして出願手続を済ませる。さらに発明者である先生の協力のもと、当該技術を使ってくれる企業を探索して技術移転契約を結び、そのライセンス料を発明者である大学の先生に還元して更に研究を進めてもらい、残りの一部をTLOの維持費用、特許出願等の費用に充てるという、いわゆる「知的創造サイクル」を回すということが、達成できれば上出来となる。 TLO(テクノロジー・ライセンシング・オーガニゼィション~技術移転機関の略)が設立される以前の産学官連携、技術移転は先生方自らの人脈だよりであったり、前述したように大学の研究協力課が片手間的に行わざるを得ないなど、本格的なものとは程遠いものであった。そこで、産学官連携を加速させ、日本の技術力を取り戻すという大義のもと、前述の大学等技術移転促進法が制定され、当該法律の施行を受け、バスに乗り遅れるな式に各地に雨後の竹の子のように経済産業省承認のTLOが設立された。北海道地区では、北海道大学や北見工業大学等の教授先生、北海道経済産業局の担当官の方が尽力して北海道に所在する企業に株主になって貰い、北海道全域の大学等をカバーする広域の技術移転機関として、株式会社形式で北海道ティー・エル・オーが設立されるに至ったのである。 しかし、大学の先生の発明といっても玉石混交、というより玉石石混交の状態であり、単に特許出願を済ませたからと云って簡単にライセンス先など見つかるものではない。このころから、大学の研究費は、産業化が見込める分野などに重点配分されるようになってきており、助成金などの競争的資金の割合が増加し、先生方も研究費の確保に汲々とされておられるのが、傍から見ていても感じられた。この傾向は今も継続されていると思うが、産業に応用できない分野の軽視につながっているように思われるというのは、言い過ぎだろうか。 大学の外部組織である学外TLOが扱う事のできる発明は、本来的に発明者(大学等の先生)が保有している「特許を受ける権利」をTLOへ譲渡してもらえる発明ということになる。つまり、大学等に所属する先生方から、「特許を受ける権利」の譲渡を可能にするには、学内の発明評価委員会によって大学として当該発明に関し、職務発明として承継しないという宣言がされた発明であることを意味する。つまり、当該発明に関する活用等については、発明者である先生方の自由に任せるということが、大学等の内部で認定された発明ということになる。 要するに私の仕事は、先ず発明の発掘から始まり、「特許を受ける権利」の譲渡手続、その発明に関する特許性及びマーケット性の評価、社内手続、事務所への出願依頼、ライセンシングと一気通貫で行うことが求められたのであるが、上述の通り大学発明は玉石石混交であり、正直簡単に済む話ではなかった。発掘した発明に関してTLOとして取り扱わない場合、つまり、特許出願をお断りをするには相応の理由が必要であるし、そのことを伝えた際に、先生方から怒りをぶつけられることも多少あった。特許出願の有無は研究費獲得の際の一つの判断材料にもなるわけで、その気持ちも分からないわけでなない。しかし、大学の先生方というと、世間では雲の上の存在と思うかもしれないが、市井の発明者と本質は変わらないことも事実であった。 通常、大学等の先生方の発明はシーズ段階のものが多く、実用化には企業との追加の共同研究が必要となるなど、技術移転には大学発明故の困難性を伴っていた。そのため、企業には研究段階から参画してもらうための一手段として、共同出願契約を企業とTLOとが締結し、共同で出願を行うことが多くなっていったのは、必然的な流れと云える。このことは、現場のニーズを知る民、理論に強いアカデミア相互の良いところを融合し、民の仕事に関し技術的裏付けを付与する方策の一つでもあるから、共同出願自体は、産学連携にとって決して悪いことではない。理論的な裏付けのない技術は、結局伸びが頭打ちとなり、発展が阻害されるという事になるのである。 勿論、産学官連携に関し、経験があり慣れている先生の場合は、複数の研究テーマを同時進行させており、実用段階の研究、実用段階手前の研究、基礎的な研究、企業との共同研究などというように、多くのチャンネルを有しているものである。このような百戦錬磨的な教授先生の場合は、北海道ティー・エル・オーに委ねる発明をセレクトして提供されておられた。手練手管の教授先生から視れば、当時の私など、単に特許出願を費用も掛けずにさせるのに都合の良い存在というような、ヒヨッコ扱い的な部分もあったろう。特許流通アドバイザー(知財コーディネータ)は、そのような発明を見抜く目利き能力が必要であることは言うまでもない。大学内には言葉は悪いが、海千山千の色々な方々が存在するのであり、多彩・多様な経験を積んだ教授先生と渡り合うには大胆さ・豪胆さも必要となる。 一方で、先入観にとらわれることなく、提示された発明を虚心坦懐に見つめ、複眼的・多面的な視点で良さを見い出し、発明者に更なるヤル気をもって貰えるような対応に努めなければならないともいえる。要はバランス感覚が大切である。このことは、コーディネート業務のみならず、発明に日常的に接する特許事務所としても必要なことである。 この頃、大学発明の技術移転の一つの形態として、当時の経産大臣(平沼氏だったと記憶している)が大学発ベンチャー1,000社という方針を打ち出し、大学の先生方に起業を促した政策があった。確かに、その政策に沿ってベンチャー企業が生まれたことは事実である。一方で、その優劣については、その後のリーマンショックなども重なり、経営の困難さに突き当たった企業も多かったように聞いてはいるが、近年は大学発の起業が活発化しているとのことなので、当該政策もタイムラグはあったものの、一定の成果はあったのだろう。 ・国立大学の独立行政法人化の波に翻弄される 私は一兵卒として、北海道内の大学を歩き回って発明を発掘していたが、ちょうど北海道ティー・エル・オーに着任して3年ほど経ったころ、文部科学省は、国立大学の法人化という方針を打ち出し、主だった大学には特許出願や技術移転を専門に扱う、知的財産本部を設けるということが明らかとなった。一方で、全国に多く設立された承認TLOは経済産業省の所管であり、大学をめぐって一種の省庁間の対立構造が生まれつつあった。 以下、参考までに文部科学省のWEBのリンクを貼る。 文部科学省 知的財産ワーキング・グループ報告書 文部科学省 TLOの形態とそれぞれのメリット・デメリット つまり、一口にTLOといっても、大学内の組織か、或いは、北海道ティー・エル・オーのように外部組織かという相違があるわけである。当然、大学(文部科学省)の全面的バックアップを受けた学内組織に対して、外部組織が太刀打ちすることは、資金的、人的な面で難しいことが予測されたし、文科省が本格的に乗り出すということは、大学の先生方の研究内容に関して一種の統制を加えると云った側面も有していた。学内組織とすることは、極端に云えば産業化可能な科学技術を偏重する気風が生まれ、基礎的分野や人文学的分野などの軽視を招く可能性すらあるのである。産学官連携の負の側面といえよう。 このような状況を見るにつけ、私は北海道ティー・エル・オーでの仕事に対し、将来の同社の存続に不透明性を感じたし、そろそろ潮時といったことも意識した。というのは、私の個人的な事情として北海道ティー・エル・オーでの業務の傍ら、休日を利用して副業的に行っていた、自己の特許事務所の仕事が徐々に多忙となりつつある時期であった。それゆえ、これ以上北海道ティー・エル・オーの仕事を続けるのは事務所の顧客に迷惑を掛ける可能性が高く、そのため私は平成16年3月をもって、北海道ティー・エル・オー株式会社を辞する決心を固めた。 一方で、北見・オホーツク地域にある国立大学の北見工業大学の地域共同研究センターのS先生からは、同学の知財本部立ち上げに力を貸してほしいと熱心なお誘いを受けた。このお話を受け、北見に1週間おきに常駐するという条件で、同学の知財本部の立ち上げ要員として、1年間だけ文科省の産学官連携コーディネータの仕事をすることとした。 北見工業大学には私に目を掛けて下さる教授のM・H先生がおられ、M・H先生は北海道ティー・エル・オーの取締役役員でもあった。M・H先生は産学官連携に関し、熱心に活動されておられた産学官連携の先駆者であり、知財コーディネータにとっては憧れともいうべき存在だった。 私は、北海道ティー・エル・オー及び北見工大での勤務時、M・H先生からは薫陶を直接受けるとともにノーステック財団の助成金の審査委員に推薦頂いたり、北見工大の地域共同研究センターの助教授として応募しないかとのお話も頂戴した。この話は自身の柄ではないので丁重にお断りしたが、事務所の完全独立後も特許出願や商標登録出願の仕事を御紹介頂くなど、大変お世話になった。M・H先生とは一献傾けた思い出も多いのである。 このような経緯で、北見工業大学での知財コーディネータを1年勤めた後、平成17年3月に大学知財の仕事から完全に手を引き、平成17年(2005年)4月1日、自分の特許事務所を完全独立させた。 生まれ故郷である北海道での特許事務所設立は私の長年の夢であり、自宅兼用事務所という、ヨチヨチ歩きではあるが、何とか一歩を踏み出したのである。独立した一つの理由として、北海道ティー・エル・オーや北見工業大学では、外部の弁理士に出願書類の作成を依頼していたわけであるが、私自身も弁理士であり、自らの手で明細書を作成し、クライアントにより近いところで直接サポートして喜びをともに分かち合いたいという気持も正直あった。 かような次第で、平成12年から始めた大学知財の仕事は、国立大学法人北見工業大学の文科省・知財コーディネータ時代の1年間を含め、とりあえず5年間で幕を下ろしたことになる。その後、現在は自ら設立した特許事務所の所長となって、代理人として特許出願等の業務を行っている。 第8回に続く |
バナースペース
いわき特許事務所
〒005-0005
札幌市南区澄川5条12丁目10-10
TEL 011-588-7273
FAX 011-583-8655